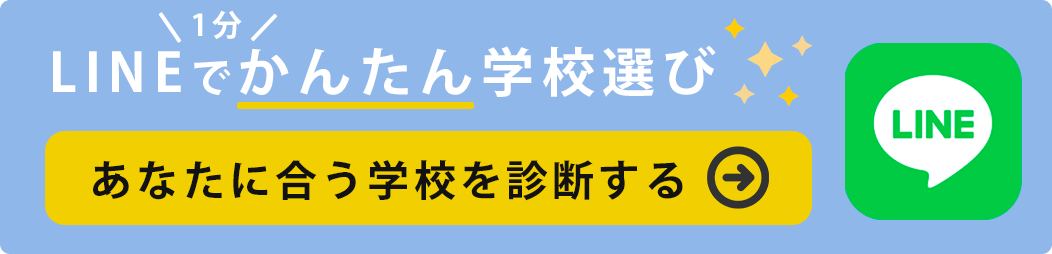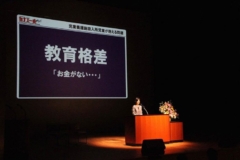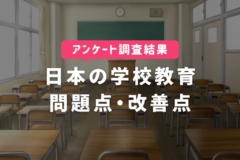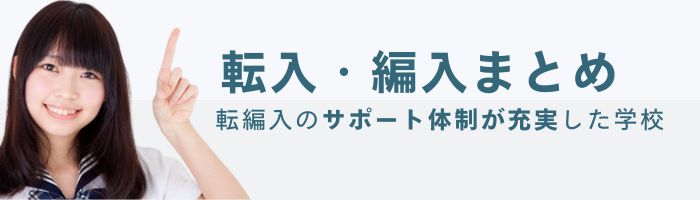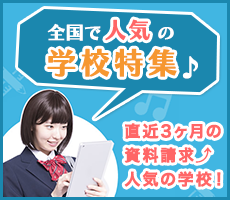年々増え続ける通信制高校。文部科学省による「学校基本調査」令和6年度速報値によると、現在は全国に303校と初めて300校以上を突破、この10年間で100校近く増えています。
生徒数も同速報値では約29万人、こちらは10年間で10万人以上の増加となっています。
通信制高校が増えた背景には、不登校の生徒の増加に伴い、その進学先として選ぶケースが増えていることや、2003年に株式会社による運営が認められて以降、設立要件の緩和がなされてきたことなど、さまざまな要因が挙げられます。
授業の内容に関しても、eスポーツやアート系、職業に結びつく専門科目など多様化が進み、興味のある領域や得意分野を学びながら自分の可能性を広げることができるようになってきました。
高校に進学したい生徒にとっては選択肢が増え、さまざまな事情を抱えていても学べるようになってきている現状。その一方、急速な変化の中で、教育の質の確保をはじめ課題もいくつか浮上してきています。不適切な運営で閉校となった学校もあれば、教育内容の面で不足している点が指摘されることもあり、制度の見直しや改善も求められてきているのです。
そんな中で、文部科学省は2021年に大学教授や定時制・通信制高校の校長などの有識者をメンバーとした「『令和の日本型学校教育』の実現に向けた通信制高校の在り方に関する調査研究協力者会議」(以下、協力者会議)を発足。
2022年には、教育課程の編成・実施の適正化や、サテライト施設の教育水準の確保などを盛り込んだ制度改正が行われました。
では2023年以降、通信制高校はどう変わり、さらに今後どのような進化を遂げていくのでしょうか。その全体像について、通信制高校の研究を進めている愛知学院大学教養部の内田康弘准教授にお話を伺いました。
通信制高校が抱えてきた「教育の質」の問題
—— 通信制高校が増え、教育カリキュラムや教育方針なども多様化が進む中で、教育の質の確保などがこれまで問題点として挙げられてきました。協力者会議でも多くの議論が交わされ、2023年には制度改正が実施されましたが、これまで通信制高校はどのような課題を抱えてきたのでしょうか。
内田先生:通信制高校は国に高等学校として認められた学校です。そうである以上、高校としての学校教育の質を担保しなければなりません。現在は、単位の認定に見合った教育を行えているかどうか、そのために適切な施設になっているか、添削指導(レポート)・面接指導(スクーリング)・試験(テスト)がきちんと行われているか、丁寧に見直していこうとしている段階にあります。
—— 具体的にどのようなケースが問題とされてきたんですか?
内田先生:これまで文部科学省が調査してきた中で、教員免許を持たないスタッフが添削指導に携わっていたり、サポート校で面接指導に携わっていたりすることがありました。また、レポートの書き方やその内容をスタッフが生徒に教えていた例もありました。こうした事例がいくつも出てきたことで、2010年代後半から教育の質を見直そうとする動きが出てきて、協力者会議も発足しました。
—— 言われたとおりにレポートを書いて提出すれば単位がもらえるなど、単位取得が形骸化していたケースもあったんですね。
内田先生:国に認められている高等学校では、主要5教科に加え、副教科や探究授業、学校設定科目などの教育課程をきちんと押さえて、修学することが求められています。全日制でも定時制でも、通信制高校でもそれは同じで、高校教育の中で求められる最低限の知識や技能、思考力や判断力、表現力などを、履修して身につけることが必要です。
—— ところが、そのために必要な環境が整っていない学校が見受けられたと。現在は、たとえば「不登校の生徒でも学びやすい環境」としてのニーズも高まっていますが、高校卒業資格が安易にもらえる学校というレッテルが貼られてしまうと、その後の就職活動で不利になるなど、結局生徒たちが不利益を被ることになってしまいますよね。
内田先生:もちろん不登校の生徒が学びやすい環境があることは大切ですが、通信制高校は制度の発足当時からずっと「自学自習」という理念を持ち続けています。通信制高校は自ら学ぶ姿勢が求められる学校であり、入学すれば何から何まで学校がきめ細やかにサポートしてくれるわけではありません。前述したように、通信制高校は高校教育を担う学校制度の一部ですから、学校側も、フリースクールや塾とは異なり、あくまでも学校として運営していくことが求められます。
制度改正で何が変わり、これからどうなっていく?
—— 2022年の制度改正(高等学校通信教育の質の確保・向上に向けた規程の改正)では、どのような点が大きく変わったのでしょうか。
内田先生:大きなものとしては、教員数です。2000年代の規制緩和の時代には、「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭の数は5人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする」とされ、教育上の支障がなければ、生徒が何人いても教員が5人いればOKということになっていました。あくまで制度上ではありますが、教員免許を持った人が5人集まれば、通信制高校を開校することができたんです。それが改正によって、「5又は当該課程に在籍する生徒数を80で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないもの」と変更されました。決してこれで十分というわけではありませんが、生徒80人につき教員を最低1人以上配置することが基準として定められたわけです。
—— 広域通信制高校など、生徒数が膨大な学校では、5人の教員では質の担保は難しいですよね。
内田先生:サポート校などのサテライト施設についても、「通信教育連携協力施設」として位置づけ、それぞれの施設で実施できる教育活動が明確化されました。具体的には、面接指導・試験等を実施できる施設は「面接指導等実施施設」(分校や協力校など)とされ、通信制高校の本校(実施校)の身分を有する教員が責任をもって行うことがガイドラインで明記されました。一方、サポート校などは「学習等支援施設」とされ、面接指導・試験等を実施できる施設ではなく、通信制高校の本校(実施校)に在籍する生徒に対して学習面や生活面での支援等を行う施設であることが明記されました。こうした明確な役割分担のもと、各施設が適切に連携・協力することで、通信制高校全体の教育の質向上につながることが目指されています。
—— 広域通信制高校では遠くて本校には通えない人のためのサテライト校があったり、普段の学習を支援するサポート校があったりと、本校以外にもさまざまな施設と連携しているケースが多く見受けられます。これを整理して、それぞれの役割を明確化することも必要だったということですね。
内田先生:施設の面でも、スクーリングを実施する場合、理科であれば観察や実験ができる施設・設備が、保健体育であれば実技ができる運動場があるかなどがガイドラインに盛り込まれました。これまで通信制高校(実施校)以外でスクーリングを実施するにあたって、必要な設備や適切な教育環境が整っていないケースも見受けられたためです。
—— ガイドラインには、強制力はあるんですか?
内田先生:強制力はなく、どう受け止めるかは各都道府県や学校によって異なってきます。厳しくチェックして整備していこうとする自治体もあると思いますし、ガイドラインをしっかり意識して運営していく学校もあるでしょう。どうなっていくかは、まだまだこれからです。
—— ということは、制度改正後の現在、すべての学校がガイドラインに沿った運営をしているとは限らないわけですね。
内田先生:通信制高校に関しては今現在、大きな変化が起きている時期と考えられます。ニーズが高まって生徒数が急増し、さまざまな生徒に対応できる環境整備が急がれている中、「各学校がどのような教育活動を展開しているのか、具体的にわかりづらい」という課題もあります。ただし、ガイドラインの策定・改正を受け、前向きに教育環境を整えていこうと努力している学校も多く見られます。
—— 生徒によっては、今まではラクに卒業できると思っていたのに、急に厳しくなったと感じることもあるでしょうか。
内田先生:高校では、全日制や定時制の場合、1単位時間=50分、これを35回(週)受けて1単位となり、卒業までには最低74単位取得することが必要です。通信制においても、全日制や定時制と同等の学習が求められており、学習指導要領に定められた各教科・科目の目標を達成することで「高校を卒業した」と言えるわけです。そうでなければ、同じ高校卒業資格にもかかわらず、全日制や定時制との「違い」ができてしまいます。繰り返しになりますが、通信制高校はあくまでも高校である、という点を意識して入学することが大切だと思います。

生徒・保護者も事前の知識&意識をしっかりと
—— これから通信制高校への進学や転入を考えている人は、どのような点を見ていけばいいのでしょうか。
内田先生:通信制高校の仕組みや学び方を事前に調べたうえで、学校説明会に行ってもらえればと思います。知識がなければ、説明会で聞いたことが中心になってしまい、入学後に「思っていたのとは違った」となってしまうこともあるかもしれません。今は、eスポーツやアート、音楽、料理など好きなことを学べる学校も増えているため、「好きなことを学んで高校卒業資格がもらえるなら」と考える人もいることでしょう。それは決して悪いことではないのですが、高校である以上、主要5教科など、卒業要件を満たす単位数(74単位以上)の取得が求められることを、忘れずに意識してもらいたいです。
—— 説明会でそこがあまり語られず、「好きなことをやって高校を卒業できる!」という点を強調されてしまうと、入学してから苦労することになるかもしれませんね。
内田先生:好きなことだけを学んで高校を卒業できるわけではないですからね。また、「不登校の生徒も無理なく学べます」といっても、スクーリングは必須で、まったく学校に行かなくていいわけではありません。たとえば、通信制高校に通っているアスリートやアイドルの方々なども、自分の活動のほかに、求められるレポートを定期的に出し、スクーリングやテストを受けているわけです。
—— 入学前にきちんと仕組みを知ることは大切ですね。
内田先生:サポート校などの連携施設についても、事前にきちんと調べたうえで、説明会で各学校に個別に確認してほしいと思います。通信制高校の本校(実施校)の学費については、国の就学支援金制度など、授業料の助成が受けられる場合もあります。ただし、サポート校は「学習等支援施設」であって本校とは異なりますので、別途費用が発生し、それは塾と同じように自己負担が原則です。通信制高校を卒業するためには、必ずしもサポート校に在籍することが求められるわけではありませんが、場合によっては、通信制高校の本校(実施校)とサポート校への同時入学を勧められることもあるかもしれません。すると、家庭によっては、それらの費用がいずれも必要となり、かなりの負担になってしまうことも考えられます。
—— 仕組みを知らないと、本校だけの授業料を見て費用を計算してしまって、後からこんなはずではなかったとなってしまうかもしれません。
内田先生:また、広域通信制高校の場合、本校(実施校)に通うのは年に数回で、日常的に通うのはサポート校となるケースが多いかもしれません。そのような中で、サポート校を学校のように感じる生徒もいると思います。サポート校に楽しく通えるのは決して悪いことではありませんが、レポートやスクーリング、テストを通じて、実際の単位認定を行うのは通信制高校の本校(実施校)だという認識を忘れずに持ってほしいですし、学校側もその仕組みを周知していく必要があります。保護者の方々には、説明会でこのような仕組みがどこまで詳しく説明されているかを、丁寧に確認してほしいです。
—— 保護者の世代には今の通信制高校はなじみがなく、わかりにくい面もあるかと思います。
内田先生:通信制高校の仕組みを理解しながら学校選択ができるように、国も、主に私立校の情報をまとめたポータルサイトをつくっています。
https://pf.tsushin-hyoka.jp/
この中の検索ページの条件検索画面では、まず学校法人か株式会社か、広域か狭域か、選べるようになっています。私立の通信制高校にはさまざまなカテゴリーがあるということが、一覧してわかるようになっているんです。検索して学校が表示されると、今度は連携協力施設数やそこで行っている教育活動を確認することができます。もし連携協力施設数が0であれば、本校に通うということになります。大変シンプルでわかりやすいので、通信制高校に関心のある生徒や保護者のみなさんには、その仕組みを理解するためにも一度アクセスしてもらいたいと思います。
—— じっくり調べて、他の学校とも比較して、自分に合った学校を選んでほしいですね。
内田先生:各学校で提供されるさまざまな学習のオプションだけに目を向けることなく、高校としての教育を受けられるかどうか、バランスよく見ることが大切です。高校教育においては、全日制、定時制、通信制はあくまで課程(ルート)の違いであり、どこを卒業しても同じ力がつくことが重視されています。つまり、高校卒業後の力はみな一定であるというのが原則なんです。そのような中で、国が果たす重要な役割は、「高校教育を受けたい、学びたい」と考える人々に、その機会を平等に提供することです。「高校の課程(ルート)が違ったために必要な力を備えることができなかった」とならないよう、国や自治体、学校運営者が改善を続けることはもちろん、入学を希望する生徒やその保護者のみなさんにも改めて、「通信制高校は学校である」という意識を持って進路選択をしてもらうことが大切だと思っています。
—— ありがとうございました。
取材協力
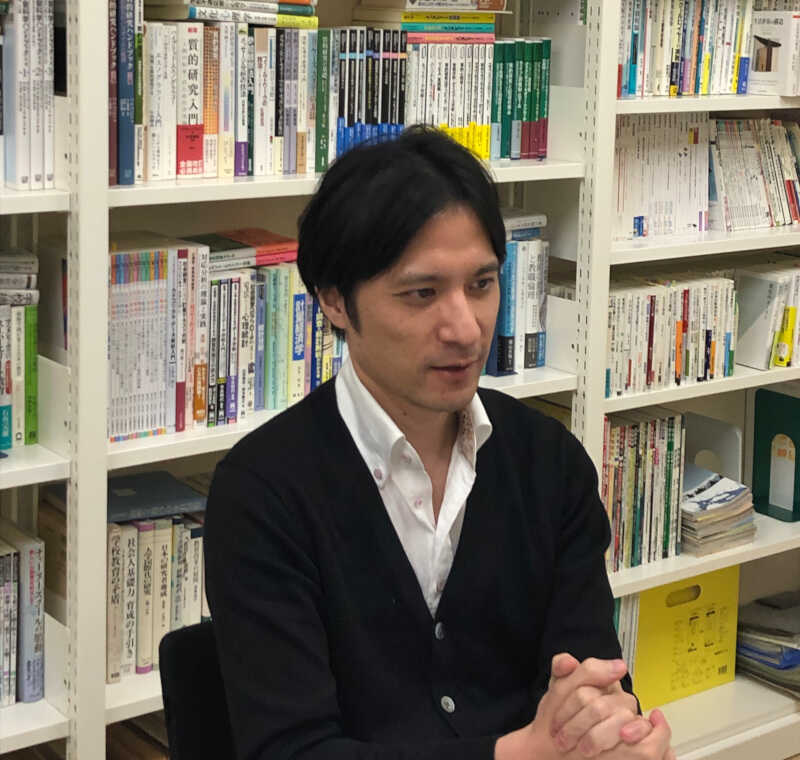
愛知学院大学 教養部 准教授
内田康弘さん
専門は教育社会学。研究テーマは学校・民間教育機関・地域社会の協働による不登校・高校中退者の進路支援。主な著書に『改訂新版 通信制高校のすべて』(共著・2023年)などがある。
<取材・文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。