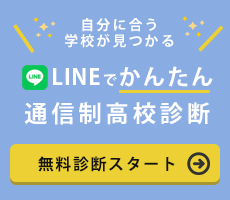選手を指導し、試合になれば檄を飛ばす――。メディアを通してそんなプロボクシングのトレーナーの姿をよく見かけますが、具体的には、どんな職業なのでしょうか? 数々の有名選手と共に戦ってきた経験を持つ、現在はフリーランスのボクシング・トレーナーである佐々木修平さんに話を聞きました。
インターハイでベスト8。そこで思い知らされた現実の壁
――まずは佐々木さんがボクシングのトレーナーになった経緯から教えてください。もともとは選手として活動されていたのですか?
私はプロでの経験はありませんが、高校・大学とボクシング部に所属していました。
きっかけはボクシングファンだった父の影響です。小学生の頃からボクシングにハマり、深夜の試合中継から衛星放送まで、テレビで見られる試合はすべてチェックしていました。ひとことで言えば、重度のボクシングオタクだったんですよ(笑)。
やがて「自分もボクサーになりたい」と考えるものの、僕の地元は岩手県の片田舎で、近くにボクシングジムなどありません。ボクシング部のある高校に進んでから、ようやく競技を始めることができました。
――当時の目標は世界チャンピオンですか?
そうですね。当初は高校を卒業したらすぐプロになって、チャンピオンを目指したいと思っていました。
でも、いざボクシングを経験してみると、これがいかに難しい競技なのかを思い知らされました。インターハイではベスト8まで進みましたが、周囲のレベルがとにかく高くて。「こいつにはとても敵わないな……」という選手がゴロゴロいるんですよ。やはり何事も、テレビで見るのと実際にやるのとでは、まったく勝手が違いますね。
幸い、ボクシングで大学へ推薦入学する話をいただいていたので、卒業後は東京の大学へ進み、教員免許を取ることにしました。将来、ボクシングの指導者として地元に戻って来られればいいな、と。
――選手として壁を感じたことが、トレーナーを目指すきっかけになったわけですね。
そうですね。大学でもボクシング部に所属しましたが、1年生の時に目を怪我してしまい、選手としてのキャリアを断念しました。それでもボクシングが好きなことに変わりはなかったので、だったらトレーナーを目指そうと考えたんです。
そこでマネージャーとして部に残り、他の部員のサポートを始めました。練習や試合の際に雑用をこなしたり、ミット(パンチを受け止める道具)を持って選手のトレーニングを手伝ったり……。これが僕のトレーナー業の始まりですね。
新卒でプロのトレーナーに。時給900円からのスタート
――そんな佐々木さんが、プロボクシングの世界でトレーナーになったきっかけは?

僕は新卒でワタナベボクシングジム(東京・五反田)に入り、トレーナー職に就きましたが、これは非常に珍しいケースだと思います。
本来は、プロボクサーとして活動していた人が、引退後にトレーナーに転身するのが一般的。しかし僕の場合は、大学のOBがワタナベジムでトレーナーをやっていた縁で声がかかり、卒業後そのままお世話になることになりました。
――トントン拍子に夢を叶えた印象ですね。
トレーナーは、資格が必要な職業ではないんです。公式な試合をサポートする際には、日本ボクシングコミッション(日本のプロボクシング競技を統括する機関)が発行するライセンスが必要になりますが、基本的には自ら名乗れば、誰でもその日からトレーナーの肩書きを持つことができます。
ただし、選手に必要とされるかどうかは別問題です。技術や知識がなければ雇ってもらえません。その点、ワタナベジムはプロ選手を大勢抱えているので、トレーナーとして1から経験を積むには理想的な環境でした。
――雇用形態としては、ワタナベボクシングジムに就職した形になるのでしょうか。
いえ、正社員扱いではなく、立場としてはバイトと同じです。最初の時給900円で、17:30〜21:00までジムで選手の指導にあたっていました。
――時給900円! 今では著名トレーナーの1人である佐々木さんですが、厳しい下積み時代があったんですね。
もちろんそれでは食べていけませんから、日中は他のバイトと掛け持ちしていました。ただし、いつ選手の試合が入るかわからないので、コンビニや飲食店など、比較的シフトの融通が利きやすい職種を転々としていましたね。
のちに、世界チャンピオンをはじめとする有力選手を担当させてもらえるようになるにつれて、時給は少しずつアップして、最終的には1300円まで上がったと思います。
それでもギリギリの生活ではありますが、寮に住まわせてもらっていたこともあり、どうにかトレーナー一本で食べられるようになりました。
試合に負けてしまった選手をどうサポートすべきか?
――トレーナーの仕事内容とは、具体的にどのようなものですか?

ジムには複数のトレーナーがいて、それぞれに担当選手が割り振られます。ワタナベジムは大所帯なので、多い時は10人前後の選手を同時に担当したこともありました。
選手がジムにやって来たらマンツーマンで練習につきそって、アドバイスをしたりミットを持ったり、全面的にトレーニングのサポートをします。そして試合が決まれば、トレーニング計画と同時に減量の指導も行いますし、対戦相手を分析して作戦を立てることもあります。
試合前日には選手を計量に連れていき、減量で衰弱しきった選手をできるかぎりケアし、翌日の試合に備えます。
当日は、試合開始の2時間前に会場入りすることが多いですね。リングをチェックしたり、バンテージ(拳を保護する包帯)を巻いたりして、30~40分前からウォーミングアップを始めます。
――そしていざ試合が始まれば、セコンド(※競技者の介添人)につくわけですね。
そうですね。ラウンドが終わって選手がコーナーへ戻ってくるたびに、汗を拭いて顔にワセリンを塗り(※打撃を受けた際の裂傷を防ぐため)、状況に応じてアドバイスを送ります。
なお、もし試合中に選手が負傷して出血した場合は、止血作業を行なうのもトレーナーの大切な仕事です。具体的には、大きな綿棒のような道具にアドレナリン液を塗り、傷口に押しつけて、一時的に血を止めるんです。この技術を磨いておくのも重要ですね。
――選手が勝った場合と負けた場合では、試合後の対応はどのように変わりますか。
勝った場合は、僕はさっさと帰っちゃいます(笑)。メンタル的には何も心配することはないでしょうし、あとは仲間と祝勝会でも何でも勝手にやってくれ、と。
問題は負けた場合です。ボクサーはその試合のために毎朝走り、厳しい練習に打ち込み、そして過酷な減量を乗り越えています。つまりはそれだけ1試合に賭ける想いが強いわけです。だから、負けてしまった時は、僕は何も言わずにそばにいてやるようにしています。
もちろん、不甲斐ない試合をしたのであれば叱ることもありますが、そうでないなら下手に言葉をかけるのは逆効果です。家に帰るまでのすべてをそっとサポートし、本人にまだやる気があるのなら、次の試合に向けてまた一緒に頑張る。その繰り返しですね。
現在はフリーランスで活躍。プロボクサーから指導のオファーが
――トレーナーとしての佐々木さんのキャリアを語る上で、欠かせないのが元世界チャンピオンの内山高志さんの存在です。世界タイトルを11度も守った、伝説的なチャンピオンでした。
内山さんとの関係は、トレーナーとしてはちょっと特殊でした。彼のほうが6歳上で、アマチュア時代からボクシング雑誌で見ていた憧れの存在です。内山さんは練習メニューも自ら考えるし、誰に言われなくてもとことん自分を追い込めるストイックな人なので、僕はただ言われるままにミットを受けたり、練習環境を整えたりするだけでした。
でも、その時期に学んだことはやはり計り知れず、内山さんが世界チャンピオンになり、防衛を重ねていく過程に立ち会えたことは、トレーナーとしての自分の大きな財産です。
――ワタナベジムを離れてからは、どのような活動をしているのでしょうか。
現在はフリーランスの立場で、プロボクサーの指導にあたっており、それなりに忙しくさせていただいています。
――待遇面にも変化がありましたか?
時給で働いていた時に比べれば、生活は格段に楽になりました。声をかけていただけるのも、やはり内山高志というボクサーのトレーナーを務めさせてもらったキャリアが大きいですね。
――最後に、これからボクシング・トレーナーを目指す人に、アドバイスをお願いします。

トレーナーに必要なのは、忍耐力だと思います。もちろん、知識や技術は大前提で、研究熱心でボクシングが好きな人であれば、引き出しは自ずと増えていくでしょう。そのうえで、時に思い通りにならないボクサーをコントロールし、共に戦い、育てていくには、やはり我慢強さが必要です。
選手が負けた時には自分も激しく落ち込むことだってあります。でも、これほど熱くなれる仕事は他にないと僕は思っています。自分が担当する選手がチャンピオンになる瞬間に立ち会えるのは、トレーナーならではの醍醐味。その感動を何度でも味わいたいから、今もこうしてトレーナー業を続けているんです。
(企画・取材・執筆:友清哲 編集:鬼頭佳代/ノオト)
取材協力

佐々木修平さん
ボクシングトレーナー。1985年、岩手県生まれ。東京農業大学卒業後、ワタナベボクシングジムのトレーナーに就任。2010年1月、担当選手の1人である内山高志がWBA世界スーパーフェザー級チャンピオンの座に就き、以降、2016年末までおよそ7年に渡りキャリアを共にする。2010年には優れた実績を残すトレーナーに授与される「エディ・タウンゼント賞」を「チーム内山」として受賞。
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2020年2月29日)に掲載されたものです。