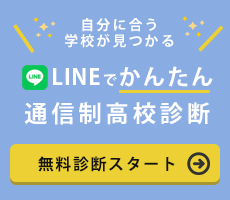2017年7月1日(土)、東京・渋谷で「不登校とマイノリティ」をテーマにしたトークイベントが開催された。登壇したのは、立場も経歴もそれぞれ違う4名。不登校になった経緯や当時学校で感じた違和感などについて、トークが進んだ。
●登壇者

今井紀明
認定NPO法人D×P(ディーピー)理事長。高校生の時、子どもたちのための医療支援NGOを設立し、当時紛争地域だったイラクへ渡航。現地の武装勢力に人質として拘束され、帰国後日本社会から大きなバッシングを受ける。その後、通信制高校や定時制高校の生徒が抱える課題に気づき、2012年にNPO法人D×Pを設立。

恩田夏絵
ピースボートグローバルスクール コーディネーター・一般社団法人ひきこもりUX会議代表理事。小学2年生から不登校になり、ひきこもり、リストカットなどを経験。定時制高校卒業後、人生最期の旅のつもりで地球一周の船旅へ参加したことをきっかけに、NGOピースボートに就職。

室井舞花
教科書にLGBTを!キャンペーン共同代表・NextCommonsLabディレクター・Love is Colorful主宰。2013年に東京都庁で同性パートナーと結婚式を行う。2014年より、教育現場で多様な性について教えることを目的にした「教科書にLGBTを!キャンペーン」を展開中。著書『恋の相手は女の子』(岩波ジュニア新書)。
●司会

武田緑
一般社団法人コアプラス代表理事。教育の重要さと、日本の教育の課題に気づき、大学生のときにコアプラスを設立。多様な人たちがそれぞれ自分を生きられる社会を目指し、教育関係者に向けた、学び・つながり・エンパワメントの場づくりを行なっている。

武田:本日司会を務める一般社団法人コアプラスの武田緑です。よろしくお願いします。私は学校の先生向けに学びの場、交流の場を提供する活動をしています。
恩田:恩田夏絵です。よろしくお願いします。私は不登校の当事者です。定時制高校を卒業後、現在は国際交流NGOのPEACE BOATで働いています。ひきこもり状態にあったり、生きづらさを抱えている女性だけが参加できる「ひきこもり女子会」も主催しています。
室井:室井舞花です。よろしくお願いします。私は性的マイノリティの当事者として活動しています。教育現場で多様な性について教えることを目指す「教科書にLGBTを!キャンペーン」を行っています。
今井:今井紀明です。よろしくお願いします。僕は通信制高校、定時制高校の生徒が抱える課題解決のためのNPO法人D×Pを主宰しています。具体的には、高校と提携して授業を受け持ったり、高校生が集える場所を作ったりしています。
不登校、対人恐怖症、性的マイノリティ……生きづらさの原因は?

武田:今日のテーマは、「不登校とマイノリティ― 学校を切り口に、子ども・若者の生きづらさに迫る」です。まず「生きづらさ」について考えたいのですが、恩田さんはリストカットをしていたときがあるんですよね。
恩田:はい。20年前は不登校児は本当にめずらしい存在で、今のように理解も進んでいなくて。「学校に行かない子は悪い子」「学校に行かないと大人になれないよ」と言われていました。今だったら「学校行かなくても大人になれるわ!」って突っ込めるんですけど(笑)。当時は、「私は学校に行くことがどうしてもできなかった」「生きていく資格がない」と思ってしまって。
それで「死にたい」と思ったり、言ったり、リストカットしたりしていたんですけど、今考えると「もっとうまく生きたいのに、生きられない」という意味の「死にたい」だったように思うんですよね。言葉通りの「死亡したい」ではなかったんだろうな、と。
今井:恩田さんは定時制高校に通われていたんですよね?
恩田:はい、神奈川県の定時制高校に通っていました。そこで初めて、いろんな年齢の人たちがいる集団に入ったんですよ。それまで私がどうしてもなじめなかった「学校」って、同じ年齢の男女だけがいる場所だったから新鮮でした。そもそも人って、年齢も性別も考え方もいろいろじゃないか、と気づいて。
さらに、19歳のときに「地球一周の船旅」のピースボートに乗って、本当にさまざまな背景を持つ人に出会ったんです。それで、「生きていけるな」と思えました。こんなにいろいろな人がいていいんだ、と。そして、そのままピースボートに就職までしちゃって(笑)。どうしても学校に行けなかった私が勤続12年。驚きですよ。
武田:学校って特殊な場所で、学校の中だけでしか通用しないルールや常識があって、それが一般社会より厳しい面もありますよね。中には、どうしてもなじめない人もいる。実は、学校の中で生きづらいのは子どもたちだけじゃなくて、「学校で生きづらい、働きづらい」と思っている先生たちもいます。「もっとこういう場所だったらいいのに」「でも『前例がない』って言われてしまう」とか。
「生きづらさ」の話題を続けますね。今井さんは、対人恐怖症だったとか。
今井:そう、なんで対人恐怖症になったかというと、人質になった経験があるんですよ。
(会場ざわめく)

今井:高校生のときに、イラクの子どもたちのための医療支援NGOを設立したんです。それで現地に行ったんですけど、武装勢力に人質として拘束されてしまい……。なんとか助かったのですが、帰国後に日本人からものすごくバッシングを受けたんです。地元の札幌の道を歩いているときに、いきなり殴られたりとか。
武田:知らない人にいきなり殴られて。
今井:そうです。それで対人恐怖症になって、事件自体のPTSDもあって、パニック障害にもなりました。4~5年はかなり生きづらさを感じましたね。周囲のみんなのおかげで、なんとか立ち直れましたが。
武田:大変でしたね。「生きづらさ」について、室井さんはどうでしょうか? 性的マイノリティであることのカミングアウトはどうしてました?
室井:学校生活は特に大きな支障なく過ごしていました。友人も多かったと思います。ただ、私は、特に小中学生時代に2つのことを絶対に言わないようにしていました。一つは「父子家庭であること」、もう一つは「同性愛者であること」。それを明らかにしないことで、表面上は特に苦しむこともなく学校生活を送っていました。
カミングアウトは、マイノリティである自分自身を認めること
武田:カミングアウトしにくいマイノリティな属性って、いろいろなものがありますよね。セクシュアリティに関することだったり家庭だったり地域だったり……。
ちなみに、私は被差別部落(※)出身者です。地域の小中学校を卒業したあと、高校以降は「どこの中学出身?」「どこに住んでる?」と聞かれるので、それがカミングアウトのタイミングでしたね。
※住んでいることや、出身であることで差別を受ける地域。関西以南に多いとされる。日本に昔存在した身分制度の名残。
室井さんが、自分の性的な傾向について自覚したのはいつ頃でしたか?

室井:私自身のことの前に一般的な話をすると、「LGBT」とひとくちにいってもいろんな意味合いが含まれています。近年「LGBT」という言葉が広く認知されるようになってきましたが、頭文字になっているレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー以外の性的マイノリティも含めた総称として「LGBT」と使われていることがほとんどです。性自認(※)もあるし性的指向もある。性自認について自覚するのは保育園・幼稚園の頃~小学校低学年の頃が多いとされていますね。そして、性的指向については「もしかしたらマジョリティな性的指向と違うかもしれない」と気づくのが小学校高学年から中学生くらい、いわゆる思春期にあたる第二次性徴期の頃が多いといわれています。
※性別についての自己認識。生物学的な性別と、性自認との間に食い違いが生じる場合も。
私自身は「女性が好きなのかも」「もしかして自分自身、女性ではないのかもしれない」と思い始めたのは小学校5年生くらいのときですね。中学2年生のときに初めて人を好きになって、それが女性でした。でも、「これってたぶん口に出してはいけないんだろうな」と思って。ちょうどその頃に、保健体育で思春期についての授業があって。教科書の中で、「思春期になると、誰もが『異性』に関心を持つようになります」という記述があったんです。それが、自分がマイノリティに属する人間なんだ、と自覚した決定打でした。
武田:その経験が、現在の「教科書にLGBTを!キャンペーン」につながっているんですね。

室井:私が学校に通っていた2000年代初頭は、メディアの中で自分と同じような立場の人を見つけるのが難しかったんです。いたとしても、テレビのバラエティ番組の中でいじられるポジションだったりして。上戸彩さんがドラマ「3年B組金八先生」の中で性同一性障害の生徒を演じたのも、この頃です。「性的マイノリティの認知を広げる」という意味では確かに大きな一歩だったと思うのですが、同時に、あの役柄に対しての批判的な……ある意味素直なコメントを耳にしたりして。
当時、学校の同級生の中にも、先生たちの中にも、LGBTを理解している人はいないように感じました。先生が(手の甲を片頬にあてて)「俺、こっちじゃないし」と発言していたり、「オカマ・ホモ・レズ」という言葉を、おそらくマイナスなイメージで使っていたりして。その言葉を聞くと、ビクッとしていましたね。
武田:それはつらかったですね。
室井:教科書の記述、バラエティ番組での扱われ方、教師の発言などから、「自分は“間違って”いる」と感じてしまっていました。自分は変なんだ、と。もしも自分の“間違い”が明らかになったときに、学校の中でどうなるんだろう、という恐怖がありました。当時、私は学校以外に所属しているコミュニティを持っていなかったので、学校からはじき出されたときにどうしていいかがわからなかったんだと思います。
今井:その状況だと、相談できる人が思いつかないよね。
室井:そうなんですよね。自分の内面について相談できる人もいなかったし、父子家庭っていうのもあって、自分の身体の女性らしい変化についても親に話せなかったし。
武田:それで、性指向を自覚してから、中高生時代はまったく誰にも言わなかったと。
室井:中高生のときは、「恋愛に興味がないキャラ」という設定で生きていましたね。
武田:「人に言えない」というのも壁の一つだけど、自分が自分のことを認識するのも、壁だよね。セクシャリティって、自分を構成する要素の一つだから。
室井:そうなんですよ。ホモフォビア(同性愛者嫌悪)っていう事象があるんですけど。その同性愛嫌悪の感情を誰が育んでいるかというと、もしかして当事者自身なんじゃないかと……。
18歳のときに初めて「私、女の子が好きなんだ」と人に言えたんですが、そのときも「レズビアン」という言葉はどうしても使えなかったんです。使ってしまうと、それまで学校で耳にしてきた「レズ・ホモ・オカマ」という分類に自分が入ってしまうんじゃないか、ということに対する嫌悪感があって。20代になってから、当事者である自分自身の中にセクシュアル・マイノリティへのネガティブな感情があることを認められるようになりました。
武田:当事者自身の嫌悪って、ほかでもありますね。たとえば、日本に暮らしていて、かつルーツは外国にある子どもが、それを隠して生きていたりとか。そうすると、親や祖先への否定と同時に、自分への否定につながってしまう。自分を構成する要素に対するネガティブイメージがあると、自己否定になってしまう。

恩田:社会全体に、「これが普通である」というイメージが存在する気がしますね。そして、「普通じゃないことは表明しにくい。「お母さんが日本人じゃないことは普通じゃないから言えない、恥ずかしい」とか、「同性を好きになることは普通じゃないから言えない」とか、「学校に行ってないことは普通じゃないからダメ、受け入れられないとか、「授業参観にお母さんが来ないからうちはおかしい」とか。言葉として思っているわけじゃないんだけど、「普通じゃないことは言わない方が良くて、言えないことはダメなこと」になっている。言えないことに関しては、自分を否定してしまう。だから、ありのままの自分を認めること、取り繕わずにそのままでいられる環境というのは重要なんだと思います。
子どもたちが学校で触れる、教師の“無配慮”な発言
室井:そのコミュニティの中でどうしてもカミングアウトしないといけないわけじゃなくて、自分で自分を認めていればそれでいいんだと思うんだけどね。でも、「学校」という一つのコミュニティにしか属していないと、そういう考え方もできずに、自己否定につながっていく。
武田:私は学校の先生たちに関わる活動をしているから、先生たちの中に、良い人で悪気は全然ないんだけど、「無配慮な人」たちがたくさんいるのもわかる。
室井:それ「良い人」か?(笑)
武田:いや、たぶんね、そこは分けて考えるべきだと思うの。「良い人か・悪い人か」と、「配慮ができる・できない」は別問題。無配慮な人は、誰かを傷つけてやろうとは思っていない。でも、たとえばプリントを配るときに「お母さんに渡してね~」と言っちゃうとか。
室井・恩田・今井:あ~……。

室井:お母さんがいない家庭があるかもしれない、と想像できていないんですね。
武田:私はそれを「アンテナがない」と表現しているのですが。アンテナがある人とない人では、使う言葉が違うんですよ。
プリントを配るときも、アンテナがない人は「お父さんがいて、お母さんがいる。これが当たり前でしょ」という思いがにじみ出てる。直接言葉にはしてないんですけどね。
父子家庭の子がいるかもしれないし、母子家庭の子がいるかもしれないし、お母さんが2人の家があるかもしれないし、お父さんが2人の家庭があるかもしれない。おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしているのかもしれないし、親戚のおうちにいるのかもしれないし、施設で暮らしているのかもしれない。配慮のない人は、それを想像できない。
私が取り組んでいる活動で、学校の先生向けの「言葉」についてのワークショップがあるんですよ。「教室にはいろんな子どもがいます。その中で、この言葉たちが青信号か黄色信号か赤信号か、考えてみましょう」っていう。
一例を挙げると、学校の教室の中で生徒が、別の生徒に「お前彼女いるの?」と言っている。これは青信号か黄色信号か赤信号か? こういうワークショップをすると、アンテナのある・ないは如実に表れますね。こういう活動を通じて、配慮のある社会、多様性を受け止められる社会へ進んでいければと思っています。
恩田:アンテナがない人……すごくわかります。私が不登校だったときに、先生が「学校楽しいからおいでよ!」って誘いに来るんですよ。「楽しくないから行ってないんだよ!」っていう(笑)。「もしかしたら楽しくないのかもしれない」ということを想像しないし、不登校の当事者である私の気持ちを汲み取ろうともしていない。世の中に自分と違う受け取り方がある可能性を考えていないんですよ。

今井:不登校の本人自身が、学校に行かない理由をわかっていないことも多い気がします。僕が通信・定時制高校の生徒たちと関わっていく中で、元々不登校だった子に理由を聞くと、「わからない」って言う子も多いんです。それはもしかしたら僕に言いたくないだけかもしれないし、簡単に口で説明できない複合的な理由があったのかもしれないけど、自分自身がわかっていないパターンもあると思うんですよ。でも、親も先生も理由を求めるじゃないですか。なんで行かないの、と。だけど、そもそも「なんで行かないの?」という質問自体が、さっき武田さんが言っていた「アンテナのない発言」なんですよね。それは、そもそも「学校には行くべき」という固定観念から出ている質問だから。「この年齢の人はみんな学校に行くべきだけど、なんであなたは行かないの?」という質問なんです。
武田:アンテナのなさ、配慮のなさは、固定観念に縛られていることと関係があるんですね。
通信・定時制高校の教師は多様性に気づきやすい

武田:固定観念といえば、学校の先生たちと接する活動をしていて、「今までこうだったからこうあるべき」みたいな学校内のルールに驚くことは多いですね。学校が変わる必要があるのは明らかです。
今井:僕が、教育に関わる活動をなぜ通信・定時制高校からスタートしたのかというと、通信・定時の先生は、多様性に気づきやすい環境だからなんです。さまざまな生徒がいる中で、生徒一人ひとりを自立まで持っていくのが学校の力だけでは難しい、ということに気づいている。外部組織との連携が必要だ、と先生たちも思っているんです。
具体的には、僕のところのNPOがハブになって、学校と、地域の大人や飲食店や企業などをつないで学校を一般社会に近づけていく、という活動をしています。提携高校は、関西と札幌で現在24校あるんですけど、全日制高校は、まだちょっと外部連携に積極的でないというか、閉じている感じがしますね。
武田:学校って難しいんですよね。何か改善すべきことがあるとするじゃないですか。それを何とかしようとしたときに、「問題が起きた」ということで、バッシングされて、さらに組織が硬直化していくんですよ。とにかく「問題」が起きないように、どんどん閉じていく。だから、何か改善する余地のあることに気づいたときに、指摘して責めるんじゃなくて、一緒に考えていきましょう、というスタンスでないと、前に進まなくなると思います。
今井:そう、「協働」が答えの一つですよね。それは文科省もわかっているはず。でも、外部と連携しようとしたときに、信頼できる人材が少ないんです。学校の外部パートナーが育っていない状況だと思うので、そこに耐えうる外部組織としてこれからも邁進していかねばと思っています。
学校の外部にある民間の組織は、行政ができないことをやれるところでもあります。税金で動いていなくて、制約が少ないから、行政よりもはやく動ける。うちのNPOはほとんど寄付で活動していて、僕がチャリティーのためにサハラ砂漠マラソンを走ったり、クラウドファンディングで応援してもらったりしています。
質問タイム

Q.教員を目指している大学生です。理解を広めるためにLGBTのことを学校で取り上げると、逆に嫌だと思う当事者がいるのではないかと心配です。どのようにしていくべきなのでしょうか。
室井:これ、すごく良い視点の質問ですよね。実は、私のような人が活動していることを嫌だと思う当事者もいるんですよ。自分は穏やかに暮らしたい、LGBTについての活発な議論提議や人権運動は望んでいない、やめてくれと。
教科書にLGBTの記述をしてほしい、という活動についても、よく、「寝た子を起こすな」っていう批判があるんです。触れずに、「ないことにしておこう」という。でも、私は違う考えを持っていて。というのも、そこで触れないでおいたことで、その場では傷つかないかもしれないけど、これから先の人生、その子が傷つかないといえるのか、と。本人の正しい理解と、周囲の正しい理解を進めることが大切だと思っています。
ただ、気を付けたいのは、「性は移ろうものである」ことを忘れないこと。特に、思春期の性自認、性指向は移ろいやすい。だから、定めないことに対する尊重が必要だと思います。答えを求めすぎずに、余白を残しておくことが大切です。
あと、どういう文脈でLGBTを扱うかも重要です。ダイバーシティの授業の中で扱うのはすごくいいなと思います。世の中にはいろいろな人がいて、その中に、異性愛者だけではなく、同性を好きな人もいるし、見た目の性と自覚している性が違う人もいるし……と。それから、先生の中にも当事者がいることを忘れたくないですね。
Q.子どもが不登校です。どう声をかけたらいいのかわかりません。そして、子どもの気持ちが理解できない自分がつらいです。
恩田:学校に行きたくない理由はあるのかもしれないし、ないのかもしれない。無理やり学校に行かせたところで、それで自己肯定感が削られることもあります。学校に行かなくても幸せに生きている人はいますから、まずは安心してほしいです。
私の場合は、不登校の間のことを思い出すと、ずっと禅問答をしていたようだったなと思うんです。毎日毎日、家にいながら、ずっと考え続けていました。普通にごはんを食べたり、ゲームをしたりしながら、いろんなことについてずっと考え続け、答えを探し続けていたんです。そういう「一回休んで、立ち止まっていろいろ考えたい」と思っている人を、無理やり学校に行かせてもしょうがない。
保護者の方がこのイベントにわざわざ来て、悩んで質問しているだけで素晴らしいことだなと思います。無理やり子どものことをすべて理解しようとしなくてもいい。まずは受け止めることが大切だと思います。“愛しているがゆえに将来が不安”なら、まず将来のことを不安視するより前に“愛している”というシンプルな事実を伝えてほしいです。
武田:私もサポートの立場で教室に入ることがあるんですけど、「明らかに教室の速度がこの子に合ってないな」みたいなことはよくあります。それを、「ペースが合わないよね。もうちょっとこうしてみる?」みたいな感じで、ほがらかに現実的に対応している先生もいれば、「なんでできないの!」みたいな意味のない反応をする先生もいて。まわりの大人が、「人ってそれぞれペースが違う」と思っているか、「まわりのペースに合わせられるようにならないとこの子は生きていけない」と思うか、で子どもの生きづらさはだいぶ違うでしょうね。

学校と生きづらさにまつわるさまざまな話題が展開された今回のイベント。近年やっと可視化されてきた問題に対して、今後どうしていくかを真剣に考える場になったのではないだろうか。
また、トークイベント後に参加者が、「一見マジョリティに見える人の中にも、苦しんでいる人がいることは忘れたくない。まだ可視化されていない、名前の付けられていない苦しみに対しても『ないこと』にしないようにしたい」と話していたのが印象的だった。
どんな人もある点ではマイノリティであり、ある点ではマジョリティである。誰もが多様な視点を持てば、学校や社会も少しずつ変わっていくはずだ。
(田島里奈/ノオト)
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2017年7月19日)に掲載されたものです。