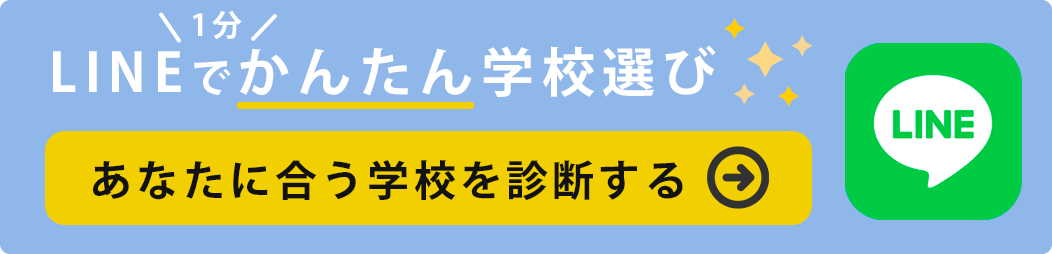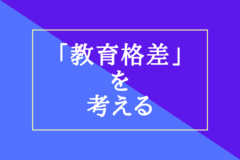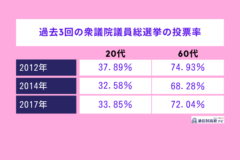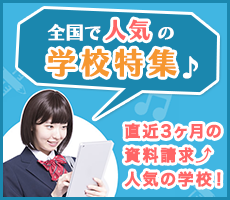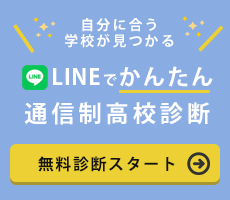10代に入るあたりから始まる反抗期。中学生や高校生になると反抗が激しくなり、親としては心配になってしまうこともあるかもしれません。
ただ、最近の子どもたちには反抗期がなくなってきたという話も出ています。
明治安田生活福祉研究所が2016年に全国の親子に調査したところ、自分に「反抗期と思える時期はなかった」と答えた親は、男性28.1%、女性26.4%。
一方で15〜29歳の子どもは、男性42.6%、女性35.6%と、反抗期を感じていない人が増えていたのです(「親子の関係についての意識と実態」より)。
もうひとつ、この調査では「親からほめて育てられたかどうか」も調査されており、そちらでは親(世代)より子ども(世代)のほうが「ほめて育てられた人」が増えているという結果が示されました。
この結果だけを見ると、「子どもをほめれば反抗期は抑えられる!」と思う人もいるかもしれません。
しかし、カウンセリングオフィスAXIAの心理カウンセラー・蔵野まどかさんは「反抗期は、子どもが大人に成長していく上ではとても大切なこと」だと言います。
今回は、 蔵野さんに子どもの反抗期と対応する保護者の心得について話を伺いました。
反抗期を「ほめ育て」で抑制しようと考えないで
反抗期に手を焼いている保護者の方は、「ほめて育てれば反抗期がなくなるなら…」と考えてしまうかもしれませんが、まずは反抗期とはどういうものなのかを理解してほしい、と蔵野さんは言います。
「成長の過程には思春期という、自分なりの考え方や感性が培われていく時期があります。そして反抗期の『反抗』という態度は、思春期における自我の芽生えに伴う自己主張の手段のひとつ。反抗期があることは、お子さんの成長にとって大切な過程であると言えますので、ほめ育てに関わらず、思春期の関わり方として反抗を抑えることが目的にならないことが重要です」
ほめ育ては、あくまでも子どもの健全な自己肯定感を育むことに優れた方法のひとつであり、そのやり方にも注意が必要だと蔵野さん。
「前提として、肯定してはいけないところまで肯定しないこと。これがきちんとできている必要があります。肯定すべきでないところをも肯定してしまうと、怒られない・否定されないという環境がつくられ、要求を通そうと反抗する必要がないために子どもは反抗しないだけ、といった状態を生みやすくなります。
反抗期があることよりも、実は主張が通らない場面での悩み方や解決方法の見つけ方を学ぶ機会がないことのほうが、将来にとってとても重要な問題です。社会に出て他人とぶつかったときの葛藤する力の乏しさにより、折り合いの付け方が上手くない大人になる可能性があります」
方法を間違ったほめ育てによって、他人と生きていくうえで必要な能力が身につかなくなってしまうこともあるとのこと。
なお、ほめ育てをするのであれば、こんな点に注意するといいそう。
「成長に応じて身につけていく子どもなりの意見を、どのように主張させてあげられるかを考えて、そこにほめ育てを活かすのがいいと思います」
子どもが物事を真剣に考えて意見をぶつけてきたとき、何かに挑戦したいと言ってきたとき、それを頭ごなしに否定せず、はっきり主張したこと自体をほめながら、一人の人間として向き合っていく。
そんなやり方であれば、ほめ育ては子どもの成長にも良い影響を与えてくれるでしょう。
子どもは反抗期を経て、生きる力を身につける
反抗期を実感できない子どもや保護者たちの中には、実は「親には」反抗していないだけ、というケースもあると蔵野さんは話します。
「今はスマホやインターネットが身近にあります。ゆえに、反発心や心の葛藤を、親ではなくSNSなどを通じてネットの世界にぶつけている子どもたちもいるのです。このほかに、不安定な気持ちをリストカットなどの形で自分に向けている子どももいます」
さらに、保護者が子どもに対して「こうするのがベスト」「これをやりなさい」とがっちりレールを敷いてしまったり、自由に意志決定をして行動することを認めなかったりする場合にも、反抗期が表れないケースがあると言います。
「子どもは『言ってもムダ』『どうせ聞いてもらえない』と思い、親への自己主張を諦めます。そうしていくうちに、自己主張するすべを学べずに大人になってしまうこともあります」
もし、自己主張する経験に乏しいまま大人になってしまうと、こんな心配要素が出てくるのだとか。
- 欲求をコントロールすることが苦手になる
- 自分の行動に伴う結果に対して責任感を持てなくなる
- 自己主張ができずに抱え込み、つらい思いをし続ける
そうならないためにも、子どもにとって「親に自己主張をする」という経験はとても重要なのだとか。
子どもが親に対して自己主張しやすい関係をつくっておくことが、反抗期によって親子関係が崩れるような状況を防ぐことや、子どもが安心して大人への階段を上っていける環境をつくることにつながるのだと蔵野さんは教えてくれました。
また、反抗期はいつまでも続くものではなく、いつか終わるときが来ます。
「反抗期まっただ中の子どもも、親や自分の心との上手な付き合い方がわからず不安かもしれません。でも反抗期は自分の価値観が芽生えてきた大切な成長の証。その経験を経て、だんだんと自分の考え方の軸ができていき、家族とはもちろん、これから出会い関わる多くの人間関係の中で生きやすくなっていくはずです」
不安なときには、親も子も自分たちで抱え込まずに、カウンセラーなど専門家に相談してみてほしい、とのことでした。
取材協力

<取材・文/大西桃子>
この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。
![]() 通信制高校・サポート校を探す
通信制高校・サポート校を探す
ピックアップ

「ありえない」そう思っていた通信制高校へ進学を決めた家族の理由

【詳しく知りたい!】サポート校と通信制高校の違いってなに? 中央高等学院...

通信制高校多すぎ! どの学校に行くべきか選べないあなたへ

通信制高校を知って道が開けた 鹿島学園 先輩インタビュー

「自分でいいイメージに持っていけばいい」卒業生が語る通信制高校で学んだ...

第一薬科大学付属高等学校 広域通信制 渋谷キャンパスの3つのポイント
人気記事

名前を変えるのは意外と簡単? 改名の手続き方法を専門家に聞いてみた

頭の中を埋め尽くす「罪悪感」をどう解消する? 心理学の視点から考える、...

世界は9月! なぜ日本は4月に新学期がスタートする?

セックス経験のある高校生は10%超 学校では教えてくれない「性」の本当の話
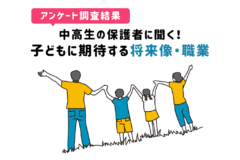
中高生の保護者に聞く!子どもに期待する将来像・職業アンケート調査
![]() 通信制高校・サポート校を探す
通信制高校・サポート校を探す
- Home
- 当事者インタビュー・調査
- 教育問題
- 子どもの反抗期がツライ… でも「ほめ育て」は子どものためにならないかも