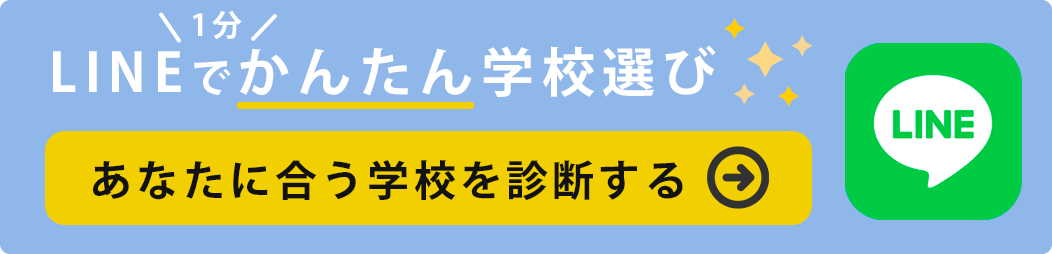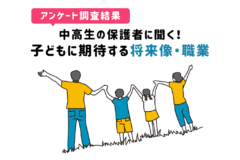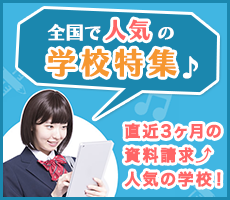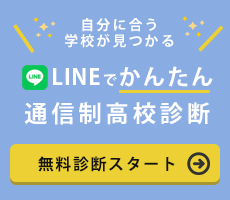他人からどう思われているか気になる。自分のことを認めてあげられない。こんなに苦しいのは、もしかして私の自己肯定感が低いから?
自己肯定感とは、「自分には価値がある」や「自分は大切な存在だ」と思える気持ちのこと。
今回は、自己肯定感とは何かを深く知ることができる本、自己肯定感を高めるヒントになる5冊をご紹介します。
『自己肯定感がドーンと下がったとき読む本』(古宮昇/すばる舎)
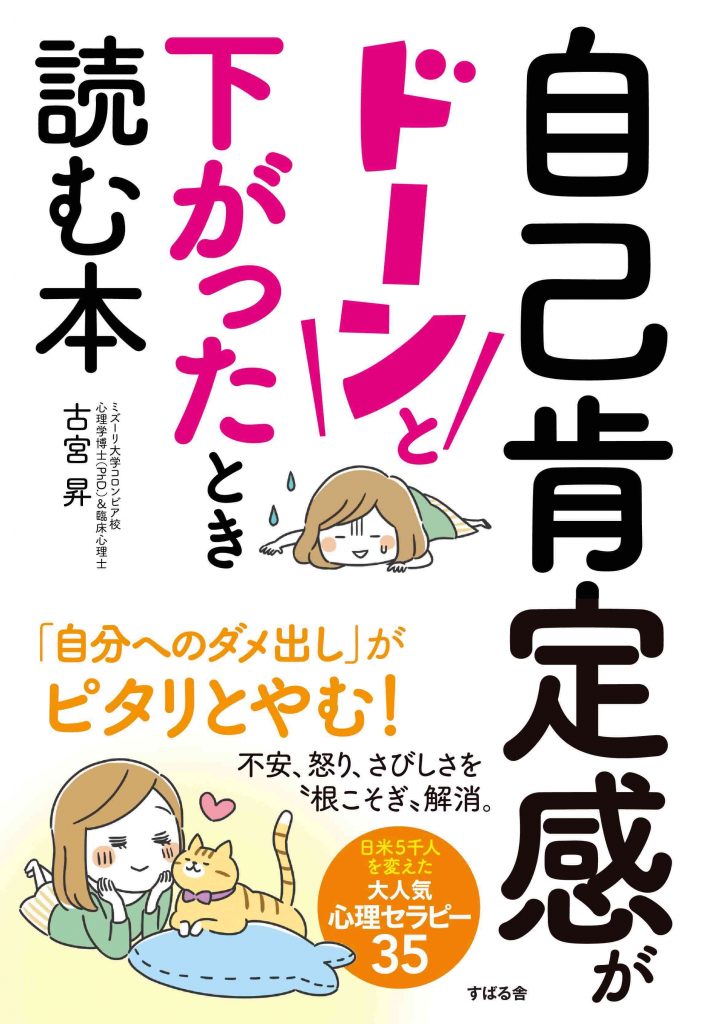
“自己肯定感が高い・低い”という言葉をよく耳にしますが、本書では“自己肯定感が上がる・下がる”という言葉を冒頭で使っているのがポイント。自己肯定感は上下するものであり、人それぞれの自己肯定感の「基本レベル」があること。この2点を切り口に、「自己肯定感=自分を大切に思う気持ち」に迫ります。
自己肯定感が高い人は落ち込んだり、自分を嫌いになったりしないというイメージを持たれがちです。しかし、本書に豊富に掲載されているエピソードから、自己肯定感が高い人は落ち込んだ自分や出来事を否定しないんだ、ということに気づかされることでしょう。
自己肯定感が高い人、低い人の特徴や、自己肯定感を高める心理セラピー、自分が本当に大切にしている価値観に気づく方法などを分かりやすく紹介しています。さらに最終章では、カウンセリングを受けることの重要性にも触れています。
「自分ってダメだな」と何度も思ったり、自分を否定し続けたりする――。そんな、自己肯定感の基本レベルが下がりやすい人、下がったままという人に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
▼『自己肯定感がドーンと下がったとき読む本』(Amazon)
http://amzn.asia/inILwz6
『嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え』(岸見一郎、古賀史健/ダイヤモンド社)
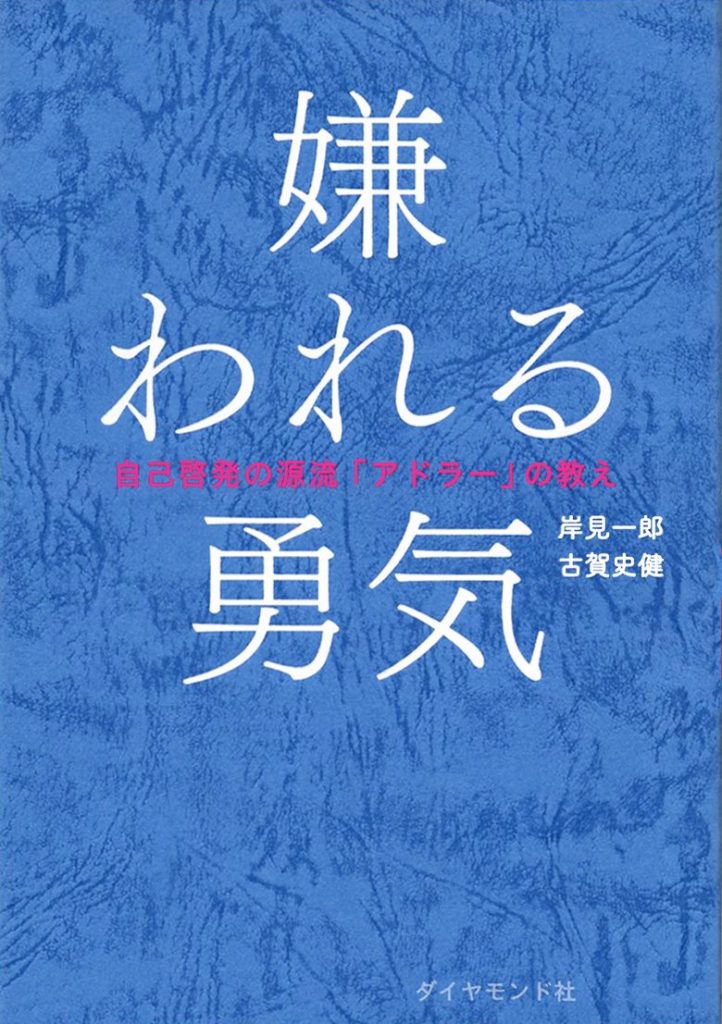
本書は、心理学者で精神科医のアルフレッド・アドラー氏の思想(アドラー心理学)を、青年と哲人という2人の登場人物の対話形式でまとめた一冊です。メインテーマを“対人関係の悩み”とし、どういう風に生きれば幸せになれるかについて説かれています。その中で劣等感や承認欲求、自己肯定や自己受容といったキーワードが登場します。
おすすめの読み方は、まず目次に目を通すこと。順を追わなくてもアドラー心理学への理解を深められるのが本書の大きな特長です。自己肯定感に悩む人であれば、目次にある「なぜ自分のことが嫌いなのか」「承認欲求を否定する」といった項目に興味・関心を持つかもしれません。目次で気になるワードを見つけたらまずそのページを開いてみましょう。
哲人の言葉に、痛いところを突かれたと感じる人も少なくないでしょう。そんな読者にとって、強い劣等感を持つ青年の存在が重要な役割を担ってくれます。例えば、「なぜ自分のことが嫌いなのか」という章では、哲人は「短所ばかりが目についてしまうのは、あなたが「自分を好きにならないでおこう」と、決心しているからです」と青年に語ります。それに対し、青年は「ええい、このサディストめ!!」と反発するのです。随所で哲人に怒ったり、反発したりする青年のおかげで、心にわだかまりを抱えずに読み進めることができるのも本書のおもしろいところです。
▼『嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え』(Amazon)
http://amzn.asia/g8cfI2R
『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』(根本裕幸/あさ出版)

本書は「自己肯定感」と「自分軸で考える」の2つをテーマに、他人に気を遣い過ぎて疲れてしまう人に向けて、自己肯定感を高めるワークを紹介しています。タイトルには、「7日間で」とありますが、実際には7つのワークに順を追って取り組むものなので、日数はあまり気にしなくて良いでしょう。
「敏感すぎる人」とは、「他人の考えや価値観(他人軸)を基準に自分の言動を決めている人」で、自己肯定感が低い傾向にあるそうです。もし、「しなきゃいけない」や「すべき」と考えるクセがついているようであれば、それは他人軸の考え方かもしれません。これでは、さまざまな価値観に振り回されてしまいます。一方、「自分が何を感じているのか」「本当は、自分はどうしたいのか」と、意識を自分に向ける(自分軸で考える)ことができれば、心を疲弊させずにすみます。
周りの顔色をうかがいながら過ごしている、いつも何かにビクビクしてしまう。そんな人におすすめ。物事を他人軸で考えるのではなく、自分軸で考えて生活していくことの大切さが学べる一冊です。
▼『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』(Amazon)
http://amzn.asia/4PeFsv0
『猫はためらわずにノンと言う』(著:ステファン・ガルニエ 訳:吉田裕美/ダイヤモンド社)
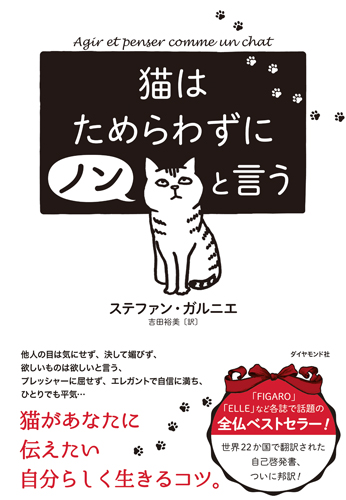
作家の著者が3本足の愛猫ジギーと暮らす中で猫に学んだ、自由な生き方の指南書。マーク・トウェインやヘミングウェイなど作家や小説家、詩人の猫にまつわる格言を引用しながら、猫の行動と人間のしがらみの対比がユニークに描かれています。
「ありのままの自分を受け入れる方法」という章では、人間の5段階欲求説で有名な心理学者のアブラハム・マズローの言葉から始まります。
「人類は種の中で唯一、自分の種を受け入れない。猫は猫でいることに何の困難も感じない。単純なのだ。猫は、犬になろうなどというコンプレックスも矛盾も葛藤も意思ももち合わせていない」
自己肯定感につながる「自分を受け入れる」という言葉は、人にとって難しいものです。しかし、猫は猫である自分に満足しているように見えます。本書は、他人が自分をどう見ているかはひとまず忘れて、自分が本当はどんな人間なのかを考えてみる“きっかけ”を与えてくれるはず。
▼『猫はためらわずにノンと言う』(Amazon)
http://amzn.asia/clYMBc9
『ええところ』(作:くすのきしげのり 絵:ふるしょうようこ/学研)
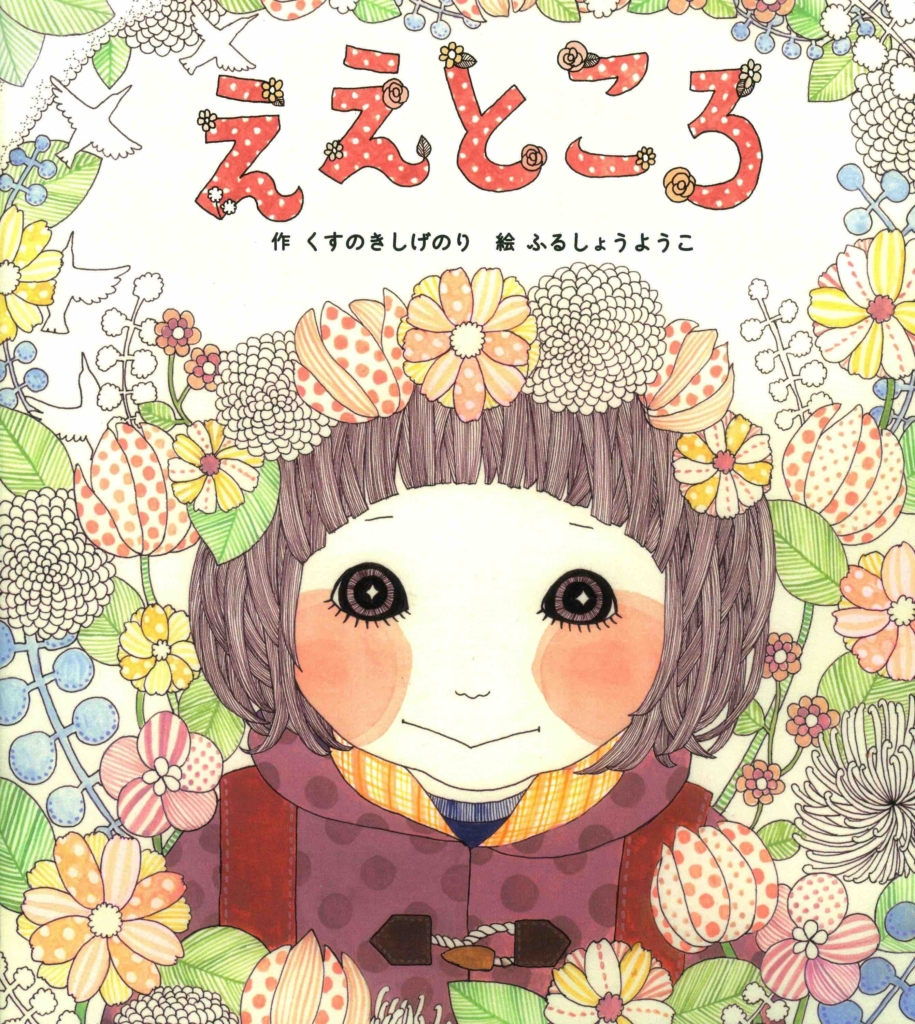
いいところなんてひとつもない――。そんなふうに落ち込む子どもの気持ちに寄り添い、自己肯定感を育む物語。関西弁のセリフが、読み手をリラックスさせてくれる絵本です。
主人公は小学1年生のあいちゃん。「わたしって、ええところひとつもないなあ」と落ち込むあいちゃんに、友達のともちゃんは「あいちゃんの手はクラスで一番あったかいんや」と言ってくれます。
まるで自分のことのように自慢するので、気づくとあいちゃんの周りにはクラスの友達がいっぱい。ところが、みんなの手をあたためているうちに、あいちゃんの手は冷たくなってしまい……。「どないしよう、わたしのええところがなくなってしもた」と、あいちゃんは涙をこぼします。あいちゃんの「ええところ」はなくなってしまったのでしょうか。そのとき、ともちゃんはにっこり笑って「けどな、わたし、あいちゃんのもっとええところみつけたよ」と、あいちゃんの手を握り……。
この絵本を読むと、大人が思うよりも子どもにとって「自己肯定感」が大切であることがわかります。また、自分の「ええところ」を見つけ出すのと同じくらい、人の「ええところ」を見つけ出せることが、どれだけ大事なことかに気づかされることでしょう。子どものいいところを褒めて伸ばしてあげたいと思うお母さんにおすすめの絵本です。
▼『ええところ』(Amazon)
http://amzn.asia/15WjvqH
いまここにいる“自分”を認めてあげよう
自己肯定感をもつ――。それは、自分自身への理解を深め、前に進んでいくことなのかもしれません。
まずは、いまここにいる自分を認めて、それからどうすれば自分のことを大切に思えるようになるのか。どうやってその気持ちを高めていくのか。自分が少しでも楽に生きられるようになる気づきを、本から得られることでしょう。
(企画・選書・執筆:水本このむ 編集:鬼頭佳代/ノオト)
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2018年8月27日)に掲載されたものです。