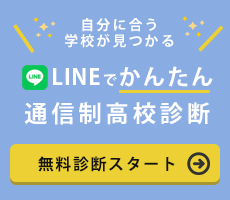「実は、私が関わった生徒のなかにも、自殺してしまった子どもがいます」――本のあとがきに書かれている一節だ。小学校教師を16年勤め、現在は市教育委員会で指導主事として活躍している荒井隆一さん。クリスクぷらすでは以前にも、荒井さんへのインタビュー(自分をさらけ出せば、子どもはかならず向き合ってくれる)を掲載した。
荒井さんが2018年12月に上梓した『いじめ2.0 ~新しいいじめとの戦い方~』(愛育出版)には、長年教育現場に携わることで見えてきた、リアルないじめの課題と提言が込められている。
いま、いじめをなくすには、どうすればいいのだろうか。
「いじめの法律」はある、けれど現実には浸透していない
滋賀県大津市で起こったいじめ自殺をきっかけに、2013年に「いじめ防止対策推進法」が制定された。これが、いわゆる「いじめの法律」だ。同法律の第11条には、「文部科学大臣が『国や都道府県、学校が、いじめを防ぎ、解決するために何をするのか』を基本方針として定めなさい」という趣旨の文言が書かれている。
この基本方針は2017年に改訂され、「いじめとけんかの違い」「早期発見のポイント」「マイノリティに対する支援」など、いじめへの対応方法がかなり具体的に示されている。荒井さんも「このとおり実践できれば、間違いなく、いじめは激減するでしょう」と述べている。
事実、基本方針を踏まえて実践している学校では、いじめを未然に防止する対策がかなり進んでいる。また、例えいじめが発生しても、初期段階で教師がチームで介入し、解消に向けた取組みがなされている学校もある。
ただ残念ながら、そういった実践ができていない学校があるのも事実だ。
「いじめゼロ」と報告している学校こそ疑え
もし年間を通して「いじめがゼロだった」と教育委員会に報告している学校があれば、それは「残念な学校」かもしれない、と荒井さんは指摘している。高い確率で、いじめを放置している可能性があるからだ。なぜ、そう言えるのだろうか?
文部科学省が3年間にわたって実施した調査によると、約9割の子どもが「いじめたことがある」「いじめられたことがある」と回答している。つまり、子どもの目線からはどの学校でもいじめは起こっているのだ。
その一方、2017年度に文部科学省が実施した別の調査では、「年間を通していじめがゼロだった」と答えた学校が約25%。明らかに子どもと学校側の意識には矛盾がある。
この数字からも、いじめを隠していたり、そもそも存在に気づいていなかったりする学校が少なからず存在する、と言えるだろう。
「観衆」や「傍観者」がいじめを助長する
いじめの質に大きく関係しているのは「観衆」や「傍観者」である、と荒井さんは述べている。観衆とは、いじめの現場を見ながらはやしたてたり面白がったりする子どもたち。傍観者とは、見て見ぬふりをする子どもたちだ。
いじめが起これば、教師の多くは加害者と被害者の対応に注目するため、観衆や傍観者の存在は見落としがちだ。国のいじめ基本方針では「いじめの四層構造」を取り上げ、加害者と被害者だけでなく、観衆や傍観者を指導する重要性が述べられている。
観衆や傍観者の数が多いほどいじめが悪質化することは、研究から分かっている。逆に言えば、「いじめは絶対に許さない」という雰囲気があれば、悪質化しないのだ。観衆や傍観者から、いじめの仲裁者へ。この変化こそ、いじめが起こりにくい環境を作るカギとなる。

いじめが起こりにくい集団をつくるために必要な「自己有用感」
しかし、次は自分がいじめられてしまうかもしれないと思うと、なかなか仲裁者にはなりにくい。また、「先生に相談しても、どうせ何も変わらないだろう」と判断している子どもも多い。では、いじめが起こりにくい集団をつくるには、一体どうすればいいのだろうか。
文部科学省の研究結果から導き出された答えは、「一人ひとりの自己有用感を高める」こと。国のいじめ基本方針にも示されているポイントである。自己肯定感はよく聞くが、自己有用感というのはあまり聞きなれない言葉だ。
文部科学省国立教育政策研究所では、自己有用感を「人の役に立った、人から感謝された、人から認めたれた、という自分と他者(集団や社会)との関係を自他共に肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する肯定的な評価」と定義づけている。
つまり、最終的には自己評価であるとしても、他者から評価されているのを強く感じることで生まれる感覚なのだ。
したがって、学校で自己有用感を高めるためには、子ども同士がお互いの良さを認め合える環境にする必要がある。「自分はクラスの中で価値がある存在である」「人の役に立つ行動をしている」「まわりから認められている」という実感を持つことができる。そんな環境を、教師やまわりの大人たちが作っていかなければならない、と荒井さんは言う。
本の中には、いじめをきっかけに「大縄跳びを1,000回跳ぶ」という目標を達成した実践や、「平和フォーラム」を開催し地域の人々を驚かせたエピソードが紹介されている。いずれも大きな成果を挙げ、新聞社からの取材も受ける事例に。自己有用感を育む手法として、ぜひ参考にして欲しい。
加害者から離れようとしない「いじめられっ子」
荒井さんは、いじめを受けている生徒に対し「いじめてくるグループから離れよう」「別のグループの子と付き合えばいい」などとすすめる。しかし実際には、なかなか関係を切ろうとしないケースが多い。いじめを受けているにもかかわらず、なぜ離れないのか。
いじめ被害者は、「もしグループを離れたら自分の居場所がなくなってしまう」「一人になるのがこわい」と感じる傾向があるようだ。
しかし、「もし気に入らない相手がいたら、お互いが傷つけあわない形で、ともに時間と空間を共有できる作法を身につけることが大切だ」と荒井さんは主張する。常に濃密な関係を求めるわけではなく、あえて距離をおいた方が良い場合もある。それは子どもも大人も同じだ。ただ、人生経験が浅い子どもたちにとって、「離れる」という行動に出るのは難しいのかもしれない。
一人ぼっちになってしまうことは、「こわい」「さびしい」といった感情を伴う。しかし荒井さんは「逃げて一人になったときこそ学べ」「孤独な時間こそ自分を飛躍させるチャンスだ」と伝えている。
孤独な時間こそ、好きなことをやり続けよう
最後に、今まさにいじめを受けているあなたへ、荒井さんからのメッセージを紹介しよう。
もしかすると、「いじめられたのは自分にも原因があるからだ」と思っているかもしれません。暗いから、わがままだから、生意気だから、かわいくないから、勉強ができないから、勉強ができすぎるから、目つきが悪いから、嘘をついたから、約束を破ったから……etc. そんなことは一切考えなくていいのです。(中略) いじめは暴力です。どんな理由も、理由にはならないのです
――『いじめ2.0』(愛育出版)p41より
あなたは悪くない。逆に「自分は一生、他人をいじめるような人にならない」と心から決意できたとすれば、それはとても尊いことなのだ。
本書には、子どもの頃にいじめを経験し、現在は各ジャンルで活躍されている著名人(中川翔子さん、吉村作治さん、蛭子能収さんなど)のエピソードが紹介されている。彼らに共通しているのは、いじめから逃げた孤独な時間によって、夢を叶えるチャンスをつかんでいるという点だ。
図書館でひたすら本を読む、家で漫画を書く、ラジオ番組にメッセージを送る、スポーツに打ち込む……。いじめられている今こそ、好きなことにのめり込めばいい。それがやがて、将来の仕事につながるかもしれないのだ。
(執筆:村中貴士 編集:鬼頭佳代/ノオト)
<記事で紹介した本>

「いじめ2.0 ~新しいいじめとの戦い方~」(荒井隆一/愛育出版)
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2019年1月6日)に掲載されたものです。