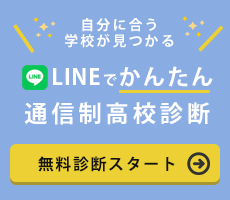「声が出ない」
大学2年生の夏、バイト先の休憩室に駆け込んで震える手で母へのLINEをした日のことを、あれから5年が経った今もわたしは忘れることができない。
何者かにならなければ、生きている理由はない──。
そんな圧力に苦しみながら生きていた過去のわたしは、知らず知らずのうちに、自分の決めた“こうあるべき”の檻の中に閉じこもっていたような気がする。
人生で初めて声が出なくなったあの日。わたしがもっと伸びやかに生きたいと心から願ったあの日。
わたしが考えたこと、決断の過程をほんの少しでもお届けしてみたいと感じて、今のこの文章をカタカタ書いています。

思えば、高校3年生の秋に突然下した「美大に入学する」という選択は、良かったのか悪かったのかわからない。
幼い頃から、びっくりしてしまうくらいに興味関心の幅広い子どもだった。得意な教科もなければ、特別苦手な教科もない。平均的にそこそこなんでもこなす。
つまりは「器用貧乏」が、当時のわたしを表現するのにぴったりのフレーズだった。
でも、それを嫌だと思ったことは一度もなかった。何をしても5段階中「4」の成績が取れる自分を、とても誇らしいと思っていたから。
そんな自分の生き方を「間違った」と初めて思ったのは、18歳の頃。高校3年生へ進級し、進路選択を迫られた4月のことだった。特別好きなことがあるわけではないから、専門学校なんて眼中にない。大学といっても、学部はおろか、そもそも文理の選択すらままならない。
現代文、数学Ⅰ・Ⅱ、英語、化学、現代社会、世界史……と、強いて挙げた得意科目だけでもこれだけある。そのほか、舞台表現や映像、心理学、音楽、テニスなど、学校の勉強以外にも好きなことがたくさんあった。その中から「ひとつ選べ」だなんて言われても、決まりようがなかった。
そんなわたしを見かねて、高校の先生は「ふう」と小さなため息をついた。
「なんでも好きってことはね、なんにも好きじゃないってことなんだよ」
そう言葉をかけられたとき、自分の中に築いてきた、ゆるやかなアイデンティティがすべて崩された気がした。
そうして、文理も、学部も、大学も決まらないまま、高校3年生の夏休みを迎えたわたしは、いよいよ途方に暮れていた。予備校の夏期講習にも一向に熱が入らないのだから、大学受験なんて夢のまた夢だと思っていた。
ところが、次の春。わたしは都内の郊外にある美術大学の入学式に出席していた。当時、興味関心の中のひとつだった「舞台表現」を学ぶために、進学先を美術大学に選んだのだ。
幸い、進学先の学科はデッサンや絵画などの試験がなく、秋口から受験対策を始めたわたしでも合格ができた。

入学して、1カ月ほどで「しまった」と思った。だって、そこには才能しかないヤツらがあまりにも多すぎたのだから。
時間も守れない、性格が個性派すぎる、座学は寝てばかり。そんな、一見すると不真面目な人だったとしても、才能さえあればのしあがっていく。
わたしが踏み込んでしまったのは、そういう世界だったから。美術大学の中で、器用貧乏が注目されることはなかった。
「詩乃の優しい性格が好きだよ」と言ってくれるクラスメイトはいたけれど、そんなのはこの世界じゃ通用しない。関係ないのだ。
すべては、努力によって作られた才能か、天性の才能によって作られている。当時のわたしは、そう感じていた。
何者かにならなければならない──。
人よりも一芸で秀でなければならない──。
模索に模索を重ねてもその答えは見つかることなく、見つかるよりも先に、張り詰め続けた糸がプツンと千切れた。
「声が出ない」と母へ送った文章を眺めながら、もう、何もかもをリセットしようかとすら思っていた。何のために生きていて、誰が自分を必要としているのか、何もかもがわからなくなってしまったから。
大学には、だんだんと通えなくなった。何もできない自分が、才能の目の前に立つことはこの上ない恐怖だった。自意識が強かったのだ。

不幸中の幸いと言うべきか、夏休みを迎えたばかりの頃に声を失っていたわたしは、夏の間をとにかく治療にあてた。
「ストレス性の社会不安障害」というやたらと重めの病名を背負いながら、睡眠薬と精神安定剤とを自分の身体に投げ込み続ける日々を過ごした。
そうすると、ほんの少しずつだけれど、声が出るようになっていった。気持ちが前向きになった。笑えるようになった。
夏休みが明けた頃。震える足元を押さえながら、久しぶりに大学の門をくぐってみることにした。その日のレッスンは「脚本を書く」というもの。そして、そのなかで選ばれた脚本を、実際に演じるレッスンだった。
クラスメイトたちの脚本がずらりと並び、講師と生徒とで、一つひとつ吟味するように選んでいく。
選ばれたのは、わたしの脚本だった。
居場所なんかないと思っていた環境で、初めて誰かに認められた。「良い」と一言、言葉をかけてもらった。ほんのかすかな自信がついて、それから頻繁に言葉を書くようになった。
そうして、文章を書くようになり、(紆余曲折を経て、)わたしは今こうして文章を書くお仕事に就いている。18歳の頃のわたしに伝えても「嘘だ(笑)」と、ばかにされるような気がしているけれど。

あの大学生活を経てわかったのは、学部や専攻の枠と、自分が生きたいと願う土俵は、必ずしも同じではなくても良いのだということ。
「舞台表現の学部」に所属しているからといって、舞台表現で結果を残さないといけないわけではないのだ。
むしろ、美術大学に進学したことで得られた文章のお仕事がたくさんある。取材のお仕事で母校に出かけたことも。そんなふうに、どこできっかけが生まれて繋がるのかなんて、誰にもわからない。だから、面白い。
大学生のときに知った「別軸で山に登る」という生き方は、今もなお、活きている。たとえば、ライターとして生きると決めたときもそうだ。
若手の女性ライターが、実績もない状態でどのように生きるのか。そう考えて「若手の女性ライターが少ない領域で実績を積もう」と決めた。それがたとえパイの小さな場所だったとしても、選んでもらえる理由を作ることができれば、生き残ることができるだろうから。
当時の選択が100点満点の答えだったのかどうかはわからない。でも、今年の夏でライターとして働き始めて5年目。きちんと生活ができているのだから、大はずれの選択ではなかったのだろうな、とも思う。
人はそれを「逃げ」と呼ぶのかもしれない。本当に、逃げなのかもしれない。でも、わたしは「あいつは逃げた」と後ろ指を指されないように人の目を気にして生きるよりも、自分が胸の奥底で叫んでいる声に気づけるような人生を送りたい。
わたしは逃げた。舞台の世界から、文章の世界へ。でもそれは、自ら選んで決めたことだ。別の山に登ると決めて、舞台という山から下りたのだ。
そして、わたしはそんな自分の生き方や選択を誰よりも愛している。誰の目も気にすることなく、そう言えるから。
大切なのは、逃げたとか逃げていないとかじゃなくて、自分で何を選び取るのかだと思う。そして、その決断を誇ることなのだと。
(執筆:鈴木詩乃 編集:鬼頭佳代/ノオト)
プロフィール

鈴木詩乃(すずき・しの)
写真のWebメディアPhotoliの編集者。多摩美術大学美術学部を中退後、デザイン専門学校在学中にライターとして活動を開始。日本と世界の文房具屋さんを巡りながら文章を書いて生きている。1995年生まれ。
URL:https://note.com/shino74
Twitter:https://twitter.com/shino74_811
※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2020年2月15日)に掲載されたものです。